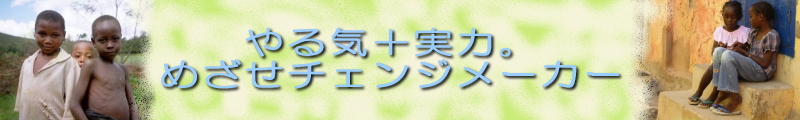「活動で結果を出すためのコミュニティ開発講座」
動画での受講者募集中!
Facebookグループ内に設置する動画視聴での受講となります。受講にはFacebookアカウントが必要です。動画は公開中です。
受講申し込みはこちらから(Facebookグループへの登録をしてください)
2019年から2022年度にわたり、有限会社人の森は、国際協力機構の実施する「NGO等提案型プログラム」の一環として、「地域住民の自立と経済的発展を目的としたコミュニティ開発のためにアウトプットと費用対効果の向上をめざしたNGOスキルアップ研修」(略称「活動で結果を出すためのコミュニティ開発講座」)を実施いたしました。当講座は終了しましたが、講義の様子を動画で受講いただけます。
2012年に実施した講座の様子です。「コミュニティ開発のためにアウトプットと費用対効果の向上をめざしたスキルアップ」という研修の意図が説明されています。よろしければご覧ください。
コミュニティ開発とは
この講座でいうコミュニティ開発は、開発途上国における農村開発、地域おこしのようなイメージで捉えていただいてかまいません。地域住民の福祉、生活改善、生産性向上、収入向上などを図る取り組みを広く指しています。関連する分野やトピックとしては、農林水産業にかかる普及活動、農業等組合活動、参加型の小規模灌漑事業など、Primary Health Care、一村一品、生活改善運動、地元産品を活かした食品加工、手工芸、観光(コミュニティツーリズムやグリーンツーリズム)、フェアトレード、参加型の環境保全、青少年活動など、地域住民を対象とした多くの分野での協力を含みます。
社会・経済環境が大きく異なる日本の農村コミュニティを想定した地域おこしの講座ではありませんのでご注意ください。
研修の目的
この研修は、コミュニティ開発にかかわる国際協力プロジェクトに従事、またはこれから従事する予定のある人材がコミュニティ住民の活動の持続性を高めるため、地域住民の基礎力強化のためのキャパシティビルディングと、地域資源を市場志向で活用するための基礎知識とノウハウを学ぶためのものです。また、特にNGO等の限られた人的資源を使って費用対効果を最大化することを目指し、援助にかかわる側のプロジェクト形成、ドナーへの提案や報告能力の向上を目指します。
研修実施方法
オンラインでの対面講座はすべて終了しました。現在公開しているのはFacebookグループ内にアップロードした動画を使っての受講のみです。
1講座のべ60時間の講義を1回分とし、基礎編と応用編に2分割して実施しました。基礎編はコミュニティの社会経済開発の基本と、プロポーザルやレポートの作成能力向上を学びます。後半の応用編ではビジネスの基本や住民が取り組むビジネスモデルの構築手法、またその実現を支援する手法などを実践的に学びます。
講義形態 |
講義時間(目安) |
特 徴 |
Facebookグループ内の動画視聴 |
基礎編:1日(1コマ(3時間)×2)×5日間 |
・自宅、海外からの受講が可能。 |
受講登録者はFacebook上に設けるグループのメンバーとなり、意見交換、交流や、また講師からのアドバイスの場とします。
研修の対象者及び選考方法
国内外でコミュニティ開発や関連分野の活動を行っている方や関心のある以下のような方々。例えばNGO/NPO関係者、学生、自治体職員、開発コンサルタント、ソーシャルビジネス/CSR活動関係者、JICA海外協力隊希望者等。経験、年齢、性別、所属は問いません。
海外協力隊経験者やNGO関係者からは「現地に行く前に受講したかった」という声が多くあります。
受講料
受講料は無料ですが、以下は受講者の自己負担となります。教科書の無償提供は終了しました。
- ・ 講義テキストの代金。購入を希望される方はFacebookグループに登録後、管理者にメッセージでご連絡ください。教科書代金・送料の支払いにかかる振込手数料はご負担ください。Amazonで購入されれば手数料無料です。
- ・ あるいはアマゾンKindle版を自己負担でご購入下さい。なおKindle読み放題を利用されている方は、すべての教科書を無料で読むことができます。
研修修了証
動画視聴の場合、受講の確認ができませんので、修了証の発行は致しません。
カリキュラム
各講座は3時間を1コマとし、30時間(5日分)の基礎編と、同じく30時間(5日分)の応用編とに分かれています。ここでは10日間での受講を例として示してあります。ただし動画では、ワークショップの部分や休憩時間が省いてありますので、視聴時間はもう少し短くなっています。
各コマに使用する教科書が示してありますので、教科書購入を希望される場合は、受講されるコマに必要な教科書をメモしてください。
各講義の動画へのリンクはこちらに設けてあります。
基礎編 コミュニティ開発の基礎・プロジェクト・マネージメント能力の向上
日 |
内容 |
第一日 |
1-2コマ 使用する教科書:国際協力の教科書シリーズ5 『地域コミュニティ開発 参加型開発・コミュニティの社会経済』 |
第二日 |
3コマ 4コマ 3コマ目と4コマ目は逆順に実施する場合があります。 使用する教科書:国際協力の教科書シリーズ5 『地域コミュニティ開発 参加型開発・コミュニティの社会経済』 |
第三日 |
5-6コマ 使用する教科書:国際協力の教科書シリーズ4 『機会均等の研修実施によるコミュニティ開発 PRRIEアプローチの基礎と実践』 |
第四日 |
7-8コマ 使用する教科書:国際協力の教科書シリーズ6 『コミュニティ開発プロジェクトのマネジメント』 |
第五日 |
9-10コマ 使用する教科書:『小論文・レポートの書き方 パラグラフ・ライティングとアウトラインを鍛える演習帳』 |
応用編 コミュニティの経済的開発等
日 |
内容 |
第一日 |
基本的な経済概念・地域資源を活用したコミュニティ開発の基礎(日本福祉大学大学院国際社会開発研究科修士課程の単位認定対象の講義です。詳しくはこちらをご覧ください。) 使用する教科書:国際協力の教科書シリーズ3 『地域産品ビジネスによるコミュニティ開発 援助を行うための基礎知識』 |
第二日 |
|
第三日 |
15-16コマ 使用する教科書:国際協力の教科書シリーズ2 『ビジネス振興と経営 ビジネスセンスを磨こう』 |
第四日 |
17-18コマ 使用する教科書:国際協力の教科書シリーズ2 『ビジネス振興と経営 ビジネスセンスを磨こう』 |
第五日 |
19-20コマ |
講座テキスト
有限会社人の森が出版した「国際協力の教科書シリーズ」等を用います。海外等遠方にお住まいの方は、教材のAmazon Kindle版を入手してください。海外から書籍版をAmazonで購入することも可能です(Amazonの配達が対応している限り)。当社から国外へのテキストのお届けはできません。
使用予定の講義テキストは以下です。Amazonへのリンクが設けてあり、それぞれの教材には書籍版とKindle版があります。
・ 国際協力の教科書シリーズ2 『ビジネス振興と経営 ビジネスセンスを磨こう』
・ 国際協力の教科書シリーズ3 『地域産品ビジネスによるコミュニティ開発 援助を行うための基礎知識』
・ 国際協力の教科書シリーズ4 『機会均等の研修実施によるコミュニティ開発 PRRIEアプローチの基礎と実践』
・ 国際協力の教科書シリーズ5 『地域コミュニティ開発 参加型開発・コミュニティの社会経済』
・ 国際協力の教科書シリーズ6 『コミュニティ開発プロジェクトのマネジメント』
・ 『小論文・レポートの書き方 パラグラフ・ライティングとアウトラインを鍛える演習帳』
講師紹介
本講座の主講師は、参加型開発などの実践者として知られている野田直人です。応用編の一部に関しては、中小企業診断士の野田さえ子が講師を務めます。
 野田直人のプロフィール
野田直人のプロフィール
国際協力分野における参加型開発の草分け的な実践者、開発ワーカー。
三重大学農学部卒業。メルボルン大学農林学部修士課程終了。
ロンドン大学インペリアルカレッジ開発学修士コース中退。
ホンジュラス、ネパールで青年海外協力隊員として勤務した後、主にJICAの専門家として、ペルー、ボリビア、ケニア、タンザニア、セネガル、マラウイ、ミャンマー、マダガスカルなどで勤務。
林業技術者としてスタートしたが、主役は住民であること、そしてプロジェクト経営の重要性に気づき、参加型開発やプロジェクト・マネージメント、地域振興へと専門性がシフト。2005年に開発協力の経験を伝えることを目的のひとつに、有限会社人の森を設立。また日本福祉大学国際社会開発科(大学院)の客員教授を務める。
1997年から「国際開発メーリングリスト」を主催。開発協力分野におけるオピニオン・リーダーの一人と目されるようになる。さらにメールマガジン「国際協力マガジン」を創刊。編集長。
著書に「タンザナイト」(風土社)、「開発フィールドワーカー」(築地書館)、「小論文・レポートの書き方 パラグラフ・ライティングとアウトラインを鍛える演習帳」「地域産品ビジネスによるコミュニティ開発 援助を行うための基礎知識 (国際協力の教科書シリーズ3)」「機会均等研修実施によるコミュニティ開発 PRRIEアプローチの基礎と実践(国際協力の教科書シリーズ4)」「地域コミュニティ開発 参加型開発・コミュニティの社会経済(国際協力の教科書シリーズ5)」(有限会社人の森)など。共著書に「国際協力の仕事」(アルク)、「続入門社会開発」(国際開発ジャーナル社)、「参加型開発の再検討」(アジア経済研究所)、「共生社会への課題」(唯学書房)など。監訳書に「参加型開発と国際協力」「参加型ワークショップ入門」「開発の思想と行動」(ロバート・チェンバース著、明石書店)など。
その他開発関連雑誌への寄稿、セミナーの講師など経験多数。
野田さえ子のプロフィール
国際基督教大学卒、オランダ社会研究大学院大学(ISS)開発行政学修士。
ADB/世銀マイクロファイナンス認定トレーナー(with Distinction)。
(財)日本国際協力システムにてODA文化無償事業における事前調査・実施促進などを担当した後、JICAヴィエトナム市場経済化支援プロジェクト事務局 調査研究員。
国連プロジェクトサービス機関(UNOPS)ニューヨーク本部環境部モントリオール議定書ナイジェリア国担当官を経て、2005年より(有)人の森取締役。
外国人を雇用する企業向けコンサルティング・研修サービス事業を行う海外人財ネットを創設、現代表。
日本福祉大学 社会人学び直し履修プログラム
「地域再生のための福祉開発マネージャー養成コース」「女性と起業」講師
日本福祉大学大学院 国際社会開発研究科 非常勤講師(2016年度より)