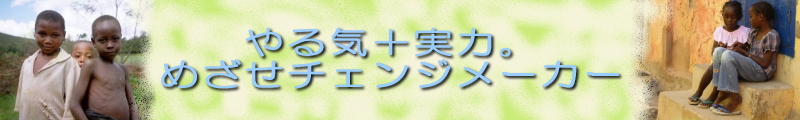成熟産業でイノベーションを起こす
~杉並区立和田中学校 藤原和博校長~
~杉並区立和田中学校 藤原和博校長~
シリーズその1/3
by 野田さえ子
「成長市場への参入がベストとは限らない。かえって成熟産業でイノベーションを起こすのがよい。特に規制などでがんじがらめに守られていてほっておかれた市場は狙い目だ」。
とある経営コンサルタントの大先輩から教えていただいたこの言葉を、今よく思い出しています。
先日、「規制でがんじがらめの成熟産業」の1つである教育の現場でイノベーションを起こしている、杉並区立和田中学校の藤原和博校長のお話を直接伺う機会を得ました。
- 約7割 ― 家に帰っても「おかえりなさい」と言われない子どもの割合。
- 約3割 ― 一人親世帯か離婚調停中か、または実質上父親不在の家庭の割合。
- 約3割~5割 ― 宿題を出してもやってこない子どもの割合。
- 約5割 ― 小学校で習う 2/3 + 3/5 の分数が解けない中学生の割合。
- 年約200枚 ― いじめ・自殺の問題に対して「心の通う授業を」といった呼びかけだけの通達の数(中学校)。
- 年約400枚 ― 上と同様の「免責文書」の類が小学校へ送られる数。
次々と家庭の崩壊と、形骸化する教育行政の実態を数字であげながら、力強く藤原校長はつづけます。
「日本の教育現場は底辺の底上げが必要」
「いじめや自殺は、親や教師、生徒たちでは解決できない。親や教師といった縦の関係や、友達といった横の関係ではなく、欲のない第三者の大人たちとのナナメの関係をいかに豊かに築けるのかが最重要」
さて、あなたが校長だったら、いったいどういう改革をするでしょうか?
 杉並区立 和田中学校 |
 藤原和博校長 |
1.「経営力」で教育再生
(1) 驚きの公開授業でブレークスルー:
まず藤原校長が着手したのは、「学校で教えられている知識と実際の世の中の架け橋となるような授業」を開催し、徹底してこれを公開しました。
地域の大人たちやゲスト講師を迎え、ブレーンストーミングやロール・プレーイングなどのスキルを駆使して、身近な社会問題を実践的に生徒たちが考える機会を提供しています。
「よのなか」科の授業は、スケジュールや内容がネット上でタイムリーに公開されており、参加したい意思があれば、一定のルールの下で、私のような「外部の人間」でも参加することができます。
「ハンバーガーの出店先はどこがよいか」、中学生たちが実際に地図をみながら、また、近郊駅の乗降客数を実際に電話して尋ねるなどして、さまざまな情報をもとにどこに出店するのがよいか、グループで戦略を練る。経営コンサルタント達がやっていることと同じことを中学生がやってのけるので、私は子どもの潜在能力にびっくりしてしまいました。
「教育の世界で儲け話?」と疑問に感じる人がいるかもしれません。しかし、この「よのなか」科では、必ず発言した人にみんなで大きな拍手を送る、それぞれの意見を尊重するなど、失敗を許し個々の子どもたちに勇気を持たせる授業進行になっています。
生徒たちも、外部の訪問者には慣れている様子。昔では考えられないくらい、外部の人間が構内をうろついています。ある意味外の目が入ることで、閉鎖的な社会で起こりがちなデメリットを解消しているような明るさを構内に感じました。
こうして、「閉鎖的」であった学校を、外部のエネルギー(ヒト・モノ・ジョウホウ等)を取り込む新しいスタイル、つまり外部とのネットワーク型の学校づくりの足がかりを作りました。
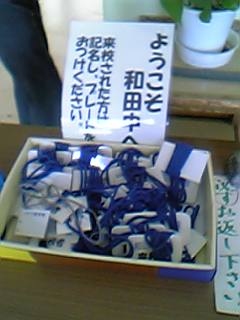 外部の見学者を受け入れる体制ができている |
(2) 生産管理の概念導入!
学校教育という現場に、経営や生産で用いられる「稼働率」や「サイクルタイムの短縮化」という概念を取り入れて「底辺の底上げ」を成し遂げています。
藤原校長の着任時の給食支給日は178日でした。給食が提供されているのかどうかというのは、教育という機会提供が1日フルに稼働していることを表し、これを指標として管理。現在では196日に向上させて授業の総時間数を増やしています。
また授業時間単位を50分でなく、45分に切り替え、その分30分の別の授業を1日1コマ増やしました。サイクルタイムを短縮化させることによって、国語、算数などの強化すべき教科を1コマ増やし、授業効率が飛躍的に伸びています。その結果、生徒たちの学習効果があがっています。
2.地域力で教育再生
「ナナメの関係」づくり:地域本部(学校支援本部)
次に着手したのは、「教師と生徒」や「親と子」といった縦の関係でもなく、「友人」同士の横の関係でもない、生徒に直接的な利害関係のない「欲のない大人」との豊かな人間関係を築くための、つまり「ナナメ」の関係を作り出す仕組み作り=地域本部を立ち上げました。
地域本部では、PTAのOG・OBが主体的に運営し、「自立貢献」の原則で卒業生や地域住民、教員養成課程の学生などさまざま立場の大人の経験や技術、知識をうまくつなげる活動を展開しています。
その1つが土曜寺小屋です。この土曜寺子屋、通称「ドテラ」では、ともすればだらだらと過ごしがちな土曜日の午前中の時間を利用して、大学生等のボランティアが生徒たちの学習をサポートしています。計算力の向上を目指したコースや、大学の教授を招いた英語のパワーアップコースも設置。
 清水たかみ 地域本部事務局長 |
 今日もドテラに多くの生徒が集まる。 見学者も。 |
 かなりハイレベルな英語のヒヤリング。 大学の先生からの授業。 |
また、子どもたちの放課後の居場所の提供として図書室の改造・拡充を行い、近所のガーデニングが得意な人が中心となり「グリーンキーパーズ」としてボランティアが芝生や花壇・稲作など学校緑化活動を担っています。
 農業を愛する人、緑を愛する人たちによって 手入れされているのがわかる。 |
 大人が手入れしている場所は荒らさないと校長。 |
 地域本部のボランティアによって季節ごとに ディスプレーがかわる。 |
 放課後寝転んで図書室にいられるよう絨毯を工夫。 |
 図書室の一角。 学生ボランティアが生徒たちの勉強をみてあげている。 |
本来家庭が担っていた学習環境の提供や放課後の居場所の確保、また先生たちが負担に思っている学校の緑の維持、コンピュータなどの新しい分野の授業準備などを、外部の人材が自立的に補完する画期的なシステムとなっています。
地域の人達に手を入れてもらった芝生やミニ水田に囲まれ、落ち着いて学習に取り組む生徒たちの姿を見ると、この仕組みがかなり機能していることが伺えました。
 生徒たちが主役の掲示物が壁面をうめている。 |
 工場の生産効率向上の鍵 5Sを思い出してしまった。 |
3.全国展開
この和田中の取り組みをモデルとして、文部科学省が来年度から4年間で中学校の1万校区に「学校支援地域本部」を設置する方針を固め、08年度予算の概算要求に盛り込む予定。計画どおりに進めば11年度にほぼ全校区に設置され、全国展開されるそうです。経営革新は教育の場でも起きています。
4.もう一つの成熟産業では?
さて、「規制などでがんじがらめに守られていてほっておかれたもう一つの成熟市場」国際協力の現場では、どういう改革ができるでしょうか。モデル事業を立ち上げ、普及の任を担う専門家の方々にとっても、この藤原校長がやり遂げた改革の1つ1つの要素が非常に参考になるのではと思います。次回は、具体的に国際協力の世界でも実施できる、革新のためのコツをお届けします。